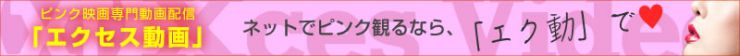佐倉萌インタビュー『アンニュイでコケティッシュ ・佐倉萌のマルチな魅力』第7回

インタビュアー 工藤雅典
第7回『帰れる場所』
【1.燃え尽き症候群と次の道】
工藤:『貪る年増たち サセ頃・シ盛り・ゴザ掻き』を監督した後だけど、監督を続けたい気持ちはありながらも、女優の仕事に戻るわけだね?
佐倉:女優もですけど、もっとオールマイティーに現場を手伝ってましたね。着付けで現場に付くこともありますし、当時、綿引さんというキャスティングマンがいたんですけど、綿引さんの手伝いでキャスティングをやったりしてました。
工藤:確か、エクセス作品のキャスティングもやってるよね?
佐倉:ええ、加藤文彦組(『三十路色情飼育 -し・た・た・り-』2002年公開)ですね。主演は木築沙絵子(女優 1966~)さんでした。
工藤:監督では一回燃え尽きたみたいな感覚があったのかな?
佐倉:ありましたね。
工藤:色々な事をやって、次に進む道を模索する時期になったんだろうね。ピンク映画の出演では、2003年だけどエクセス作品で、『高校教師 引き裂かれた下着』(監督 下元哲)に出てるね。

『高校教師 引き裂かれた下着』の2012年改題『高校教師の下半身 教え子にレイプされ』ポスター
※エクセス動画にて絶賛配信中!
佐倉:夜間学校の話でしたね。主演が橘瑠璃さんでしたっけ?
工藤:そうだね。

主演 橘瑠璃
佐倉:橘さんは面白いキャラクターの女優だったんですけどね。もっとピンク映画に出て欲しかったです。
工藤:共演で酒井あずさ(女優 1986~)さんも出ているね。
佐倉:そうですね。私は、トイレ掃除のおばさんの役だったんですけど。
工藤:ああ、そうだったね。
佐倉:夜間学校の生徒役で色んなスタッフが出ているんですよ。
工藤:そうだね、この作品で脚本をやってる監督の金田敬さんも出ていたね。
佐倉:そうですね。
工藤:この脚本も良かったけど、金田さんは本当に面白い脚本を書くよね。
佐倉:そうですよね。金田さんの脚本は粘ちっこくて、ヌメヌメしてて好きなんですよ。
工藤:そうだね。佐倉さんも好きな世界観なんだね。
佐倉:酒井あずささんは、エロかっこいいですよね。若ぶらないと言うか、本当にかっこいい熟女。若作り全然興味ありませんみたいな雰囲気で。

酒井あずさと橘瑠璃

竹本泰志と酒井あずさ
工藤:酒井さんは、ピンク映画の女優さんには珍しいタイプかもしれないけど、ゴージャスな役が出来るんだよね。華やかさがあってね。で、コミカルなところもあるし。バイプレーヤーとして貴重だよね。
佐倉:そうですね。
【2.林由美香の遺した言葉】
工藤:2005年の6月26日に仲の良かった林由美香さんが、突然亡くなって、それがきっかけで、一時期ピンク映画を離れたと聞いたんだけど。この時、31歳だよね。その理由は何だったの?

林由美香『熟女温泉 うまのり』より

林由美香『熟女温泉 うまのり』より
佐倉:先ほど話した、京都旅行の河原の話でもありますけど、ピンク映画に出るのも良いけど、摩耗するというか、自分を削り取られないようにしてね、と言われていたのが、凄く印象に残っていて。突然亡くなって、凄く愛されていた人ではあったですけど、何か働き過ぎていたのかなという気もして。
工藤:確かに、膨大な量の作品に出演しているものね
佐倉:ふと立ち止まった時に、自分が業界に慣れ過ぎたというか、声がかかったら「はい、はいっ」と(現場に)行くタイプだったんですけど、もう一度、きちんと脚本を読むところからやらせてもらえないかなと思った時に…。
工藤:なるほどね、確かに、脚本も読ませずに何日の何時にここに来いみたいな。
佐倉:そして衣装はこんな雰囲気でとか。
工藤:現場に衣装持ってきてとか、ちよっと安易な作り方が横行してたかもしれないね。
佐倉:ちょうどそんな時に、ある作品で、クランクインの三日くらい前だったのかな、ある助監督から電話がかかってきて、「何々組で」と。「ああ、その監督なら前に一回だけ仕事したことある」と思ったんですけど、「これから来れますか?」と言われて会社に行ったら、他のキャストと本読みが始まっていて、そこで本を渡されるんですけど、その前に電話で衣装も持ってきてくださいと言われているような状態で、「何々役で」と言われて、本を読む前に「何日と、何日空いてますか?」と聞かれて。「そうじゃなくて、この本を読んで、出演しますか?」と、そこから聞いてくれよ、と思った時にプチッと来ちゃって。その時、「この本なら、私じゃなくても出たい人が沢山いると思いますよ」と言って断っちゃいました。そこから、ちょっと距離を取った時期がありました。まあ、今はね、行きますけど(笑)。
工藤:その話を聞くと自分も反省するところがあるな。さすがに女優さんにはないけど、なじみの男の俳優だったら、役柄の説明をする前に、「この日空いてる?空いてたら頼むよ」とか言っちゃうものね。
佐倉:助監督の時から知ってるような若い監督だったら、本作りがギリギリになって、急に出演を頼まれても、「うーん、しかたない。出るよ」ってなりますよね。可愛いから(笑)。
工藤:でも、制作側からの事情で言うと本当に助かると言うか、地獄に仏というか、「急なお願いなのに、本当に出てくれてありがとう」という事があるからね。
【3.ピンク映画を離れて】
工藤:この後ピンクを離れて、けっこう一般映画の仕事をするのかな?2005年に『ヒナゴン』(監督 渡邊孝好)という映画に出てるね。
佐倉:これは長い撮影でしたね。1か月ちょいくらい、広島県の田舎でロケでした。私は、ちょっと出演と、後はずっと現場で方言指導してました。
工藤:じゃあ、広島出身という事があってキャスティングされたって言うことかな?
佐倉:そうですね。女性の方言指導は私が担当して、まずカセットテープに(台詞を)吹き込むんですけど、男性は吉岡睦夫さんがやって。現場は、全部私がついて。井川遥(女優 1976~)さんが出演してたんですが、真夏で凄く暑かったので、私は方言指導なのに日傘をさしてあげたりして。井川さんに「もう、やめてください」とか言われて(笑)。
工藤:スタッフ指向がここでも出たんだね(笑)。この後に参加した、のが『KAMATAKI -窯焚-』(2005年 監督 クロード・ガニオン)だね。これは、どんな映画?
佐倉:信楽焼の窯元の話なんですけど、元々、前作の『リバイバル・ブルース』(公開 2004年)に急遽出演したのがきっかけで、声をかけていただきました。この作品も、衣装合わせまではしたんですけど、終えた後に延期になり、それから1年延びたんですよね。10月~11月くらいの1か月半くらい信楽(滋賀県甲賀市)にこもって撮影したんですが、出演は、3日くらいで、後は料理番ですね。スタッフ、キャストの食事を全部作りました。
工藤:へーえ、本当?!
佐倉:朝、昼、晩全部です。実際に陶芸家の窯を借りるんですけど、実際に窯焚きをするので、その人たちの分の食事も作ってましたね。藤竜也(俳優 1941~)さんが主演なんですけど、私は、一夜の相手をするバーのママ役でした。現場にいる時は、ずっと藤さんのガールフレンドとして振舞わせていただいて。まあ、役作りですよね。藤さんの役作りは凄くって、インする何週間も前に、現地に住み込んで、もう地元に慣れるところから始まるんですよ。
工藤:ふーん。そんな役作りをしたんだ。
佐倉:相手役は、吉行和子(女優 1935~)さんで、お二人の空気感が何か立ち入っちゃいけないような雰囲気があって。
工藤:藤竜也さんは、日活のロッポニカという一般映画のシリーズの『行き止まりの挽歌 ブレイクアウト』(1988年製作 監督 村川透)に主演したんだけど、私は助監督で付いていたんだ。藤さんは日活出身の俳優じゃないですか。日活では、ロマンポルノが始まったりして、中々出演の機会が無かったんだよね。久々に日活に戻って主演をするということで、張り切ってね、これは伝説なので本当かどうかは分からないんだけど、朝の9時からの衣装合わせなのに、6時には撮影所に来て所内を走り回って、ウォーミングアップしていたという話があるんだ。
佐倉:しそうですね(笑)。藤さんは、撮影が終わると、スッと現場から去る方なんですよ。私は、自分の出番が終わってもずっと現場にいるタイプだったんですけど、撮影が終わると藤さんご本人が運転される車に乗せていただいて宿舎まで戻るようになったんですね。藤さんがおっしゃるには、「役者は魔法使いなんだから、魔法を使う時が終わったら、さっさと消えた方が良いんだよ」みたいな事を言われたんです。
工藤:ほう。
佐倉:クランク・アップしたその日の夕方には、焚火で台本を燃やしてお終い。「うわあ、もったいない」と思うんですけど、これは自分の中で終わった作品だからという事なんでしょうね。
工藤:うーん監督としては複雑だね。次の作品に新たな気持ちで取り組みたいという気持ちもあるのかな。
佐倉:共演していたアメリカ人の俳優を誘って、一緒に燃やしてましたね。
工藤:そうか。面白いね。
佐倉:圧倒的にカッコいいですよね。
工藤:クロード・ガニオン監督はどんな人?
佐倉:すごく長いスパンで物事を考える人ですね。
工藤:当時、日本に住んでいたのかな?
佐倉:住んでいたのは昔ですよね。『keiko』(製作1979年)を撮っていた頃は住んでましたし、『KAMATAKI -窯焚-』が終わってからも、『カラカラ』(製作2012年)を撮っていた頃は沖縄に住んでいた事がありましたね。一度仕事をしたら、10年、20年と繋がりを持っていたいというような、すごく温かい人なんです。
工藤:そうなんだ。
佐倉:『KAMATAKI -窯焚-』では、琵琶湖の近くのホテルで藤さんとベッドシーンがあったんですが、監督が藤さんに「彼女はスペシャリストだから、任せた方が良い」とか言ってくれて(笑)。藤さんとは、撮影の前の晩に、膝を突き合わせて打ち合わせをして、今回は前貼りはどうしますか?とか細かく。藤さんが「できれば僕は貼りたくないんだ」というので、「分かりました、私も貼りません」と。
工藤:ほう。
佐倉:藤さんは『愛のコリーダ』(1976年公開 監督 大島渚)がセンセーショナルになり過ぎて、トラウマになっていて、あの役をやった事が良かったのかどうかという思いに苛まれた時期があったそうで。
工藤:なるほど、そうなんだ。
佐倉:クロード監督は、すごく現場の雰囲気作りを大切にしてくれる人なので、とてもリラックスした雰囲気で撮影できました。監督自身がお茶目に、半分手で目を隠してキャーキャー言いながら「さあ、これから撮るよ、OKかい?」みたいな感じで(笑)。でも、カラミに不慣れな女の子の助監督がいたんですけど、カラミを真後ろから真剣に見ていて、「お前、その場所から見るのは止めろ」と(笑)。
工藤:ハハハ、カラミではスタッフでも入っちゃいけない角度があるものね(笑)。
佐倉:でも、素敵なベッドシーンが撮れてました。この前の作品でも内藤剛さんとのカラミがあって、娼婦の役だったんですけど、たかだか15秒か20秒くらいのシーンなんですけど、見せ方とか全てが良かったって言われて、そこで惚れていただいて、この作品に呼ばれたんです。
工藤:でも、なるほどね。カラミのスペシャリストかあ。ピンクの現場だとさあ、撮影の時間が無くて、見も蓋もなく、何でも良いから早くカランでくれ!みたになる事もあるものね。反省だなあ。雰囲気作り大切だよねえ。
工藤:2005年以降は、どんな活動をしていたの?
佐倉:月蝕歌劇団とか、ずっと舞台でしたね。月蝕歌劇団には、12年くらい続けて客演をしてました。ピンク映画では、アテレコですね。色々な監督の作品でアテレコはやってました。

月蝕歌劇団公園「夢の久作 少女地獄」2010年(撮影:平野勉)

月蝕歌劇団 寺山修二没30年記念認定事業連続公演「百年の孤独」2013年
ポスターを背景に佐倉萌
工藤:2010年に、突然のエクセス復帰をしてるね。黒川幸則監督の『ある歯科医の異常な愛 狂乱オーガズム』に出演したわけだけど、これはどんな経緯なの?

『ある歯科医の異常な愛 狂乱オーガズム』ポスター
★エクセス動画にて絶賛配信中!

主演 立木ゆりあ
佐倉:これは、カメラマンが村石直人さんですよね。村石さんが推薦してくれたのかな。
工藤:村石カメラマンとはどんな仕事を?
佐倉:村石さんとは飲み友だちでした(笑)。たぶん現場は、1本か2本しかやってないんですけど、共通して良く行くお店があったんで。
工藤:村石とは、日活の同期なんで、若いころは私も新宿で良く一緒に飲んでたよ(笑)。
佐倉:これは、リアルに私の大穴の空いた虫歯を撮影されたんです。

看護師役・ほたると佐倉萌

佐倉萌
工藤:虫歯狙いのキャスティングだったのかな(笑)。
佐倉:たまたま、治療してない虫歯が奥歯にあったんですよ。
工藤:黒川監督とは面識はあったの?
佐倉:Vシネの現場ですね。助監督時代の黒川監督とは仕事をしています。
【4.出産】
工藤:2016年の6月にお子さんが生まれる訳だけど、その前後になるのかな?2016年には、かなりたくさん出演作が公開されているね。
佐倉:撮影は、全部出産の前ですね。『華魂 幻影』(監督 佐藤寿保)も撮影は2015年です。
工藤:『悦楽交差点』(監督 城定秀夫)、これはピンク映画ですか?
佐倉:ピンクです。これは、爆発的な人気でしたね。
工藤:城定君は、監督としてどうでした?
佐倉:いやあ、面白いですよ、マニアックで。この『悦楽交差点』は美術が全部城定監督なんです。元々芸大とかそっち出身なんで、凄いですよ、小道具で観察日記とかが出てくるんですけど、全ページびっちり文章が書きこまれていたり。一々、本当に美術的に細かいんです。でも、それをやるなら、もうちょっと早く脚本を書こうよ、みたいな(笑)。
工藤:私もコウワクリエイティブの時代なんだけど、竹洞君がチーフ助監督で、城定君がセカンド助監督をやってくれた事があったんだけど、(『美人おしゃぶり教官 肉体㊙教習』公開2001年 監督 工藤雅典)、その時、美術担当をやってくれたんだ。自動車教習所の話だったんだけど、普通の乗用車にカッティングシートを貼って、見事に自動車教習所の車に仕立ててくれたんだけど、それが素晴らしくて、驚いた事があったよ。
佐倉:そういうのが得意ですからね。城定組は今でも、年に数本呼んでもらってるんです。
工藤:そういう繋がりはいいね。
佐倉:でも『悦楽交差点』の時ですね、お腹に、どうも子供がいるらしいと感じながら仕事をしていたのは。お腹に、何かいる、という状態だったので。『悦楽交差点』の直後に、加藤儀一組に着付けで3日間付いて、そしてVシネに出て、その後、吉行組に緊縛で付いて、そして『脱脱脱脱17』(監督 松本花奈)に出て、という、もうスケジュールが密々なんですけど、(お腹に)居るよね?居るよね?という感じで。
工藤:『脱脱脱脱17』では、どういう役だったの?
佐倉:この時は、もう妊娠5か月くらいだったんですけど、場末のストリッパーの役でした。
工藤:ええっ!そうなの!
佐倉:踊るし、いちゃもんを付けてきたお客さんとは乱闘するし。イブさんというSMの女王様にムチで打たれたり無茶苦茶でした(笑)。
工藤:その時は、もう妊娠してるって分かってたんだね。
佐倉:分かってました。共演してた松緯理湖ちゃんにだけ伝えて。
工藤:監督は知らなかったんだね。監督は若い人なの?
佐倉:高校3年生の時ですよ。
工藤:えっ!そうなの!!
佐倉:これも、急遽出演が決まったんです。
工藤:キャスティングには知り合いがいたの?
佐倉:キャスティングには、イオナちゃんという女優がいるんですけど、彼女が絡んでいて、ぜひ出てくださいと言われて。
【5.ピンク映画への帰還】
工藤:出産した後は、しばらく仕事は休んだんだね。
佐倉:そうですね。休んではいたんですけど、2016年の年末かな、大蔵映画の城定組の『箱舟の女たち』に1シーンだけ出演しました。それが復帰作です。2018年の佐々木浩久監督の『情欲怪談 呪いの赤襦袢』が“からみ“の復帰作ですね。その後が池島ゆたか監督の『冷たい女 闇に響くよがり声』です。
工藤:しばらくぶりのピンク映画はどうでした?
佐倉:いやあ、「私、戻って来れたよ」と言う安堵感というか、「生き残ったんだよ、私」みたいな(笑)。『情欲怪談 呪いの赤襦袢』の時、しじみちゃんも出演してて、その時、しじみちゃんにドキュメンタリー番組の密着取材があって。
工藤:ああ、それ見たよ。フジテレビの「ノンフィックス」だよね。
佐倉:はい、そうです。当日、人が多いなと思ったら、取材をやってて、しじみちゃんが、「萌さん、相談したい事があるんです」と質問を振ってくるので、「ああこれは、絶対に番組のアレだな」とは思ったんですけど、後輩の悩みに答える先輩女優“役”を演じてしまいました(笑)。
工藤:でも凄く良いアドバイスをしてたよね。
佐倉:しじみちゃんが、今の彼氏が脱ぎのある仕事に反対なんですが、どうしたらいいでしょうという質問で、それなら別れなさいと。あれはすごい反響で、あれを見て私にも、全然知らないところから仕事の話が来ましたもの。
工藤:脱ぐ仕事に対してすごく堂々とした姿勢が印象的だったよ。
佐倉:今の夫も、脱ぐ仕事に対して、どうのこうの言わないですからね。仕事と言うか表現なんで。
工藤:唐突な質問になってしまうかもしれないけど、今のピンク映画界に思う事は?
佐倉:今のピンク映画は、少しでもピンク色を無くす方向に動いているような、卑猥さが消えていっているように思えて仕方ないんです。何か健康的になっていると言うか。
工藤:それは何故かと言うと劇場中心のピンク映画から、2次使用というか、ネット配信とかCSなどのテレビ放送に重心を置いた作品作りになってきたからなんだよ。CS放送はR-15がほとんどだからね。作り手は、テレビの放送コードとかを考慮しなければならないので、確かにソフト路線になってきているね。
佐倉:そうですね、それに加えて卑猥さが薄いのは、今の若い人のセックス観なのかなとも思うんです。カラミがスポーツの一環みたいで、全然いやらしくないんですよね。脱いで、ヤッてれば良いというものじゃないというか。
工藤:そういうこともあるかもしれないね。
佐倉:ピンク映画館の館内の雰囲気を、もう少し爽やかなものにしたいというか、館内を歩き回る人を排除したいという声も確かにあるんですけど、私はそういう人たちを排除してしまったら、その人たちはどこに行くんだろうと思うんですよ。
工藤:そういう劇場の雰囲気の中で上映する事も含めての作品という事だね。
佐倉:せっかく映画を作るなら、その劇場でしか上映できない、その劇場でしか見れない作品を作って欲しいなと思いますよね。
工藤:そこは肝に命じないとね。
佐倉:地方の劇場によっては、女性だけしか入れない回とかをイベント的に設けたりしている事もあって、それもご時世だし良い事だと思うんですけど、やっぱりピンク映画館は快楽の殿堂として残って欲しいですよね。
終
※掲載した写真の一部は、佐倉萌さんの私物を提供して頂きました。