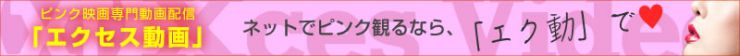浜野佐知監督インタビュー『男社会に喧嘩を売って半世紀!女性監督のピンク映画人生!!』第3回
昨年出版された『女になれない職業 いかにして300本超の映画を監督・制作したか。』が話題沸騰の浜野佐知監督。第1回、第2回が大好評を博していたエクセスインタビューの掲載を再開します。後輩監督に語られた、リラックスした浜野監督の言葉の数々には、著作とはまた違う浜野監督の素顔があります。今後、第5回まで掲載の予定。『女になれない職業』と合わせてお楽しみください。
第3回『監督を始めた頃』
【1.初監督当時のピンク映画界】
工藤:上京して、写真専門学校に入られたのが18歳ですよね?
浜野:私が監督デビューしたのが1971年だったけど、ちょうどピンク映画が変化していった時代でね、それまでパートカラーだったのがオールカラーになったりね。私の映画も『女体珍味』(1971)がパートカラーで、『十七才すきすき族』(1972)からカラーだったんじゃないかな。ポスターで「総天然色」って大きく謳ってるからね。カラミになると突然色がつくっていうのは結構刺激的だったんだよ(笑)。カラミが始まって、炬燵の上のリンゴが転がるそのリンゴの赤からカラーになるとか、黒バックにハラハラと散る真っ赤な薔薇の花びらからカラーにするとかね、監督によってそれぞれ個性が出て面白かったけどね。
工藤:なるほど。切り替えのきっかけですね。

撮影現場の浜野監督
浜野:パートカラーからオールカラー、シネマスコープからビスタ、って映画そのものも変わっていったけど、ピンク映画界で何と言っても一番大きな衝撃っていうか、劇的な変化はロマンポルノが始まったことだよね。
工藤:1971年11月からにっかつロマンポルノが公開されたわけですが、当時は、ロマンポルノをどう受け止めていましたか?
浜野:にっかつのやり方ってホントえげつなくてさ、社運をかけたポルノ路線だか何だか知らないけど、札束でホッペタ叩くようにしてピンクの女優やスタッフを引き抜いていったんだよ。(白川)和子なんか、「ピンクの仲間を裏切るようで辛い」って悩んでたもの。私にも声がかかったくらいだから、根こそぎ持っていこうとしたんじゃないかって腹が立ってさ。そりゃいきなりポルノったって、カラミを撮るノウハウなんてないだろうし、監督以外はピンクの人材に頼るしかなかったんだろうけどね。カラミを撮るって、ピンク映画が培ってきた特殊技術なんだよ(笑)。
工藤:ロマンポルノの最初期には、カラミの指導にピンク映画の監督を現場に呼んだという話も聞きました。
浜野:ほらね(笑)。でも、当時のカラミって結構大人しかったんだよ。乳首も、重なった腰も見せられないし、女優の全裸がフルサイズで見せれるのは後姿くらいだったしね。それで私が現場でカラミ撮ってたら、大井(由次)さん(1935~、制作プロダクション「青年群像」代表)が血相変えて飛び込んできてさ、「サチ、ストップ! ストップ!」って言うのよ。何事かと思ったら、「今までのカラミじゃ駄目だ、にっかつはすごいぞっ」って。それで慌てて次の日撮休にしてね、大井さんと一緒にロマンポルノを観に行ったのよ。映画の題名は忘れちゃったけど、確かSMもので今まで観たことがないような際どいカットの連続でさ、何、これ? ここまで撮っていいの? なんでこれが映倫を通るのよ、って本当にびっくりした。こりゃ負けられないってこっちも派手なカラミを撮るようになったんだけど、しばらくしたら大井さんがまた駆け込んできてね、「サチ、ストップ、ストップ! にっかつと映倫が捕まった!」って(笑)。
工藤:1972年9月にロマンポルノ4作品が、刑法の猥褻図画公然陳列罪でにっかつの監督など6人と、同幇助罪で映倫の審査員3人が逮捕された事件ですね。
浜野:うん。やっぱりね、って正直思ったよ。「表現の自由」って言うけどさ、私は性描写に表現の自由なんかないと思ってる。ピンク映画は芸術じゃないし、何を撮ってもいいわけないもん。ピンク映画の性描写ってさ、長い時間をかけて、時代時代の変化に合わせて、映倫と合意してきた結果だからね。よく映倫は敵、みたいにいう人もいるけど、私はそれは違うと思う。映倫が公権力の規制の外堀を守ってくれるからこそ、安心して撮れたんだよ。世の中でヘアヌードが当たり前になれば、何故映画でヘアを見せられないのか議論して、性行為以外でのヘアはOKになったりね。映倫に性表現の現場を知ってもらって、お互いに妥協点を探って行くのが監督や業界の仕事でもあると私は思ってきたけどね。
工藤:結局1980年の7月に東京高裁で無罪が確定しましたが、8年間の裁判は長かったですね。
浜野:うん、最初はザマーミロって思ったけど(笑)、有罪とかになったらこっち(ピンク)にまで影響するからね。我々はカラミ撮るのが仕事だしさ。でも、最近は大蔵がR15をメインにし始めたからか、時代が逆行したみたいでさ。この前映倫の審査員に会ったら、「浜野監督、ピンクに戻って来てくださいよ。最近は刺激が無さすぎて仕事してる気になりません」って笑ってたけどね(笑)。
工藤:それはピンク映画の収益の中心が、劇場からネット配信やCS放送などに移ってしまったので、劇場に来るコアなファンに向けた作品から、配信や放送を見る広い客層が受け入れやすい作品にシフトしようという生き残り戦略ではあると思うんですよね。過激な性描写の追求とは真逆ですが、コンプライアンスとか、色々な制約は昔より厳しくなっていて、その中でどう面白くするかですから、今も作り手は、けっして楽にはなってないですよ(笑)。
浜野:でもさ、そういうのをピンク映画とは言わないからね。面白くないよ(笑)。
【2.盟友との出会い】
工藤:話は戻りますが、1984年に山﨑邦紀さんと出会って、脚本・監督のコンビを結成するわけですね?
浜野:いや、出会ったのは1982年。私も青年群像で6本くらいは監督してたんだけど、そうそう思い通りに撮りたいものが撮れたわけではなかったしね。一時期リタイアしていた時期もあって、1980年に青年群像に戻ったのよ。それで、東映芸能ビデオのVシネマ(東映ロマンスビデオ)を3本撮ったんだけど、オール沖縄ロケでね。女優は2本が夏麗子で1本が日野繭子。その沖縄ロケに取材で同行したのが山﨑だったの。


夏麗子

日野繭子
工藤:山﨑さんは記者のような立場ですか?
浜野:うん。当時彼はエロ劇画誌や風俗情報誌の編集だったんだけど、東放学園で編集概論の講師もやっててね。それで、彼の学生がディレクターズ・カンパニーのシナリオに応募して上位5本に残ったんだけど最終審査で落ちた脚本があるから何とかならないか、って相談されたのよ。ところが読んでみたら男の子たちのプロレスの話でさ、しかも、主人公がインポの設定でまいったなあ、と(笑)。
工藤:男のプロレスを舞台にしたピンク映画を作る事になったんですか?
浜野:うん。「ピンクなら何でも映画になるよ」って大見え切った後だったしね(笑)。しょーがないから山﨑に頼んで男の子たちにそれぞれ女の子のセコンドをつけてカラミも撮れるような脚本に直してもらったのよ。女優は、桃の木舞と田口あゆみ。多摩川の河川敷にリングを組んだりして、結構大掛かりに撮ったんだけど、何しろ主役がインポテンツだからセックスが成就しないのよ(笑)。これ、どうやって商品にしようって考えてさ、女優二人を上半身裸にして街中でプロレスのチラシを撒かせたのよ。エキストラなんか仕込めないからその辺歩いてる人に渡すんだけど、みんなギョッとしてね(笑)。一点突破で派手なシーンを入れればお客さんを裏切らないし、配給会社もまあいいかってなるからね(笑)。
工藤:街中で女優が上半身裸でチラシ配りなんて過激ですね。
浜野:早稲田大学プロレス連盟「闘魂」の学生たちも出演してくれてね、だから台本タイトルは『闘魂伝説』(笑)。旦々舎を作る前だから、製作は「4☆プラトン」って名前でね。大井さんがミリオンフィルムの臼井一郎さんっていうプロデューサーを紹介してくれて、それで『桃の木舞 SEXドリーム』(1985)ってタイトルで公開されたのよ。
工藤:本当に、よく公開に漕ぎ着けましたね(笑)。
浜野:それがまあまあ評判が良くてさ、臼井さんが「次、撮りますか」って言ってくれて、じゃあ、山﨑と一緒に会社作ろうってなったのよ。それで旦々舎を作って続けて『密室変態調教』(日野繭子・ミリオンフィルム)と『痴漢電車・みゆきのヤリガイ』(橋本杏子・ミリオンフィルム)を撮ったの。この頃から痴漢電車ものってピンクのドル箱だったんだけどさ、私としては痴漢を正当化した映画なんか撮れないし、断ろうかって悩んでた時に山﨑から彼の劇画誌で痴漢漫画を描いていた小多魔若史さんを紹介されたのよ。小多魔さんは漫画家で痴漢評論家で、ご本人も痴漢っていうとんでもない人だったんだけど(笑)、会ってみると全く不快感のない人でね、変態とか性欲とかとは別の次元の痴漢に魅入られた悲しみ、みたいなものを感じちゃって、興味を持ったのね。それで、小多魔さんを主役に男の変態願望としての痴漢電車ではなく、女の子が主体の痴漢電車が撮れないかって思ってね、最初の『痴漢電車・みゆきのヤリガイ』は小多魔さんが原案で、山﨑が脚本、小多魔さんと山﨑が痴漢コンビ役で出演よ(笑)。
工藤:女性主体の“痴漢電車”ですか?どんな内容か興味深いですね。
浜野:内容は忘れちゃったけど(笑)、本物の痴漢を出したことがよかったのか、翌年(1986年)なんかミリオンフィルムで撮ったのが『痴漢電車・奥まで覗いて』(神谷琴絵)、『痴漢電車・我慢できない女たち』(風原美紀)、『痴漢電車・危ない隣人』(秋本ちえみ)、『痴漢電車・異常接近』(岡田きよみ)って痴漢電車ものばかり(笑)。私としては、男の妄想に水をぶっかける痴漢電車を目指したんだけど、それが成功したのは何といっても女優の力だったと思う。特に、橋本杏子と秋本ちえみ。この二人がいなかったら旦々舎初期の浜野映画は成立しなかったと思うよ。

橋本杏子

秋本ちえみ
工藤:具体的にはどんな貢献を?
浜野:二人とも度胸がいいというか、浜野ピンクを面白がってくれたんだよね。橋本には最初の『痴漢電車・みゆきのヤリガイ』で主役をやってもらって知り合ったんだけど、それまでの女の性はこうあるべきというハードルを軽々と飛び越えてきたような女優だった。演技力もダントツだったけど「浜野監督の映画は全部納得して演じられるから好き」って言ってくれてね、私がピンクでやりたいことは間違ってないって自信を持たせてくれたんだよ。浜野組を更にパワーアップしてくれたのが秋本ちえみでね(笑)、秋本とは監督と女優というより親友というか戦友みたいな関係だった。次は何をやって男どもを驚かそう、とか(笑)二人で相談してさ、新宿の駅前の電話ボックスで全裸ファックとかね、秋本も面白がってね、もう何でもやった。携帯がない時代だったからできたことだよね。今なら即、通報されて捕まってる(笑)。
工藤:そういうシーンも男の監督だと、女優は嫌々やらされる感じになってしまう場合もあるでしょうから、女優とある意味“共犯関係”を作れるという点で、女性監督の優位さもありますね。
浜野:そうなのかな。まあ、どう信頼関係を築いていくかって言うのはそれぞれの監督によって違うと思うけど、私は橋本や秋本の系譜って言うのかな、AVの子たちとはまた違うピンク女優の胆力みたいなものを受け継いでいる女優さんが好きなんだよね。風間今日子、青木こずえ(村上ゆう)、石原ゆりとか、佐々木基子さんとかね、彼女たちがいてくれたからこそ、私は好きなものが撮れて、浜野ピンクが成立したんだよ。
【3.エクセスで監督開始】
工藤:いよいよエクセスで撮り始めるんですが、そのきっかけはどんな感じだったんですか?
浜野:大体、私はエクセスで何本撮ったんだろう?
工藤:100本近いらしいですよ。
浜野:最初はにっかつ配給だったよね。1988年にロマンポルノが終わって、にっかつの直営館に配給する映画が必要だったんだろうね。その頃カメラマンの斎藤(雅則)さんが「現代映像」って制作会社を経営していてね、にっかつが現代映像に発注して旦々舎が下請けしたのよ。『盗聴魔・妻たちの性態』(1988年・白木麻耶)って作品だったんだけど、その作品でフリッカーを出しちゃってね。
工藤:フリッカーですか?
浜野:うん。照明部が初めて蛍光灯照明をやってね、テストもちゃんとしてたはずなんだけど、室内で撮影した全部のカットが使えなくなっちゃってね。結局リテイクして、1本目は大赤字よ(笑)。現像所がイマジカだったのも運が悪かったのね。東映化工(現・東映ラボ・テック)だったら、何かトラブれば撮影部より前に私に連絡が来るからね。でも、イマジカは初めての付き合いだったから現場に連絡が届かなかったのよ。
工藤:なるほど、イマジカですか。
浜野:イマジカが悪いわけじゃないけどね。ただ、やっぱりピンク業界の仲間意識みたいなものはなかったんだろうね。
工藤:その赤字は旦々舎が被ったんですか?
浜野:そりゃそうよ(笑)。買取契約の下請けだもの。
工藤:まあ、大変な事はあったけれど、エクセスの一本目を撮ったという事ですね。
浜野:そう。でもエクセスレーベルじゃなかったよね。『盗聴魔・妻たちの性態』の後、にっかつ企画部の荒井さんが直接旦々舎に発注してくれて、『ザ・スワップ しびれっぱなし』(前原祐子)、『豊丸の変態クリニック』(豊丸)の2本をにっかつ配給で撮ったの。エクセスレーベルは1989年の『い・ん・ら・ん 乱れ咲き』(前原祐子)からだと思う。
工藤:エクセスで一本目を撮る時ですが、エクセス側から何か特別な注文はありましたか?
浜野:特に注文は無かったかな。エクセスも最初は手探りだもの。それに撮影所の方式を持ち込んでいたから、案外、ちゃんとした映画作りが出来たのよ。
工藤:後にエクセスは、カラミのエグさを狙うような方針になった時期もありましたが、最初はそうでは無かった訳ですね。
浜野:最初は、それなりの予算もかけていたしね。
工藤:最初の頃の予算は1本450万円くらいだそうです。
浜野:エクセスで助かったのは、主役にいい女優をキャスティングすると別予算をくれたのよ。現場の制作費とは別に主演女優に300万円くらい出たことがあった。桜木ルイとか樹まり子とかね。
工藤:人気AV女優はかなり高額のギャラを取っていた時代でしょうが、主演女優のギャラが300万円というのはピンクとしては凄いですよね。
浜野:エクセスがエグくなったのは(笑)、にっかつビデオフィルムズから来た小松(俊一)さんがプロデューサーになってからよね。小松さんには「ピンク映画は、セックスを商品とし、観客たちを欲情させなければならない」という信念があってね、それを強要するものだから男の監督たちは嫌がったのだろうけど、私はその通りだと思ったね。だって、私はプロのピンク映画の監督だからね。会社や館主、観客が望むものを作るのが当たり前じゃない。だから、小松さんの望むような作品をガンガン撮った。私も面白かったし、小松さんも喜んでくれてね。一挙に本数が増えたのよ。
工藤:エクセスだけでも月一くらいで撮ってたんですよね。
浜野:新東宝やVシネマを入れると年に21本とか22本とかね。上野にエクセスと新東宝の小屋があって、両方とも浜野佐知作品ばかりではマズイとなってね、新東宝は“的場ちせ”という監督名にしたの。

的場ちせ監督名義の特集上映のチラシ(表)

的場ちせ監督名義の特集上映のチラシ(裏)
工藤:ああ、それで別名があるんですね。
浜野:90年代なんか、私、いつも3冊台本を持ち歩いてたからね。今撮ってるのは手に持って、他の2冊は右のポケットと左のポケットに入れて、準備と仕上げを同時にやってね。ひどい時なんか3本撮りで、同じセットで作品Aのシーン幾つ、作品Bのシーン幾つ、みたいに撮ったりね。まあ、全作品の脚本家が山﨑だったからこそ、こんな離れ業も出来たんだけどね。
工藤:山﨑さんもエクセスで監督されてますよね?
浜野:うん。1992年に新東宝と大蔵で撮ったのが最初で、エクセスは1992年12月公開の『若奥様 くい込み下半身』からかな。
工藤:何かきっかけがあったんでしょうか?
浜野:だってさ、彼の脚本がいくらよくても(現場の事情で)そのまま撮れるわけじゃないし、打ち合わせをする時間もないから、現場で私がどんどん変えちゃうわけよ。そうすると脚本家としてはふざけるな、だよね。で、初号でいつも喧嘩になるわけ。「こんな話を書いたつもりは無い!」とかさ。私も、そんな事言われたって、って言うのがあるから、「そこまで言うなら、自分で一本撮ってみろ!」と言ったのが運のツキでね(笑)。彼は大蔵が多かったけど、もう100本くらい撮ってるんじゃないかな。
工藤:ほう、山崎さんもそんなに撮ってるんですか!
浜野:うん。それから浜野組の脚本は山﨑、山﨑組のプロデューサーは私、という住み分けが出来たのね。
工藤:山崎さんは、浜野さんがずっと持っていた女性に性を取り戻すというテーマに賛同してくれたという事なんですか?
浜野:彼の方がフェミニストだったのよ。
工藤:そうなんですか?
浜野:私はフェミニズムなんて全然関心なかったし、ただガムシャラにやって来ただけだけど、その私がやってきた事に「あなたのやってきた事はフェミニズムなんだよ」と理論づけしてくれたのが彼だったの。私はフェミニズムとか何とかより、ただ男の言いなりになって、男の都合の良い女を描く映画は撮らない、という信念でやって来ただけなんだけどね。
※掲載した写真は、全て浜野佐知監督に提供していただきました。
浜野佐知監督最新情報

(発行ころから 2,600円+税 Web-shop https://colobooks.com)
浜野佐知監督の著作『女になれない職業 いかにして300本超の映画を監督・制作したか。』絶賛発売中!
*女一人でピンク映画の世界で闘いぬいた波乱万丈の半生、映画製作にかけるエネルギーに打ちのめされます。浜野監督の人生そのものが映画のよう(映画.com 書評より)