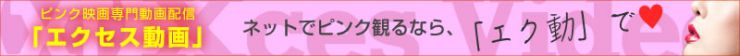ピンクの炎 第2回 「音屋の矜持」シネ・キャビン中村さんに聞く その3「シネキャビン始動」
工藤:昭和43年から昭和53年の2度目の東映時代があった訳ですが、ピンク映画と係っていく経緯はどのようなものだったんですか?
中村:セントラル録音時代も月に1本くらいは、ピンク映画をやってたんだよ。昔はピンク映画を制作する会社が本当にたくさんあったんだ。50社以上はあったんじゃないかな。
工藤:えっ!50社もですか。ピンク映画って、昔は、今想像する以上に産業として大きかったんですね。
中村:そう、大きかったんだよ。殆どが独立プロで、監督がそれぞれ会社を作って個人で受けてやってた訳だからね。
工藤:また何かのきっかけで、東映を辞める事になるんですか?
中村:ある会社の部長さんと課長さんが、俺の家まで来てね、頼まれちゃったんだよ。機材を納品したスタジオの仕上げが間に合わず、大変な事になると言うんだ。それで、俺が呼ばれて行ったんだけど、そのスタジオでは、フィルム作品の仕上げをビデオでやっていたんだね。俺は、最後にフィルムで仕上げるならフィルムのままダビングすれば良いじゃないかと言ったんだ。銀座サウンドの前身の会社の話さ。
工藤:フィルム育ちの技術者の強みですね。
中村:1週間くらい、それこそ寝ずの作業だったんだけど、ダビングしてOKという事になって、無事納品したよ。
工藤:それが、きっかけで東映から銀座サウンドに移ったわけですね。
中村:そう。銀座サウンドには、その後15年くらいいたよ。
工藤:銀座サウンド時代に、かなりピンク映画を担当したわけですね。
中村:その当時、他のスタジオは、テレビやCMの仕事が多くなっていて、ピンク映画が隅に追いやられているような状況があって、銀座サウンドにピンク映画がドーッと来たんだよ。俺は同じ映像の仕事なのに、ピンク映画をないがしろにするのはおかしいと思っていたからね。フィルムだし、好きな生音も出来るし、ピンク映画をドンドンやったよ。
工藤:当時、仕事した監督はどんな人たちですか?
中村:小林悟監督、渡辺護監督、梅沢薫監督、山本晋也監督、高橋伴明監督、中村幻児監督、獅子プロの監督の作品が多かったね。滝田洋二郎監督は助監督の頃からだからね。多い時は、月に10本くらいやってたよ。
工藤:10本もですか?3日に1本ですよね?
中村:アフレコやって、翌日ダビング。ひどい時は、アフレコやってその日のうちにダビングしてたからね。最盛期は、年間100本やってた。
工藤: それ全部にかかわった訳じゃないですよね?
中村:全部だよ。生音は、若手にやらせた事もあったけど、音楽、効果、録音、全部やってたよ。
工藤:働き者ですね(笑)。やりがいはあるでしょうけど、体力的には大変ですよね。
中村:銀座サウンドの社長はウハウハだったんじゃないか(笑)。
工藤:銀座サウンド時代は年齢的にはどのくらいですか?
中村:35歳から50歳までの15年間。
工藤:まさに働き盛りだったわけですね。
中村:そうだね。
工藤:銀座サウンド時代の印象深いエピソードがあれば教えて下さい。
中村:色々あるけどね。高橋伴明監督など若手監督が集まってディレクターズカンパニーって会社作ったじゃないですか。会社立ち上げの最初の企画で、伴明さんと、宇崎竜童さん、泉谷しげるさんが3人で1本づつ映画を撮ったんだよ(狼 RUNNING is SEX:監督 高橋伴明、さらば相棒 ROCK is SEX:監督 宇崎竜童、ハーレムバレンタインデイ BLOOD is SEX:監督 泉谷しげる、1982年劇場公開)。あれは印象に残ってる、熱気があって楽しかったね。

工藤:50歳になって、いよいよ、シネキャビンを立ち上げる事になる訳ですが、その経緯は?
中村:まず、銀座サウンドの入っていたビルのオーナーから、ビルを売りたいという話しが出て、銀座サウンドの社長から「自分は引退してスタジオを閉じたい」と相談されたんだ。俺は、まだ50歳だから、引退する訳にはいかないからどうしようかと(笑)。
工藤:それはそうですよね。
中村:木村プロって知ってる?「泥の河」とかを作った会社なんだけど。
工藤:「泥の河」は小栗康平監督の1981年の作品ですね。
中村:木村プロの社長さんは鉄工所を経営しているんだけど、元々大映かな、映画会社にいた事があって、映画を忘れられなかったんだね。自分の工場の敷地に小さなスタジオを作って、そこで映画を撮ったりしていたんだ。俺が木村さんと知り合ったのは東映時代で、木村さんの映画で生音を手伝ったのがきっかけ。意気投合して、それ以来、仲良くさせてもらって、「中村さん、何かやるときは相談して下さい」と言われていたんだ。
工藤:そういう後ろ盾が、いらっしゃったんですね。
中村:それで、スタジオをやりたいと木村さんに相談すると、木村さんの事務所の隣のスペースが空き部屋だったんだ。そこを使って良いよと。
工藤:それで、ここに移って来たんですね。まさに、渡りに舟ですね(笑)。
中村:そう(笑)。内装を自分たちで設計して、自分たちで組立てたんだよ。
工藤:正に、手作りのスタジオだったんですね!
中村:本当は内装ももっとちゃんと化粧しなきゃならないんだよね。ここで最初の仕事が小林悟監督の作品だったんだけど、二週間後にアフレコだって言うのに、アフレコスペースと録音ブースを仕切るガラスも無かった。それで、近くのガラス屋にむりやり頼んで、明日の朝までにガラスを入れてくれと。今も、そのガラスのまま(笑)。
工藤:「シネ・キャビン」という名前は中村さんがつけたんですか?
中村:そう。
工藤:最初に、このスタジオに来た時、舟の船室のような感じがしました。そういうイメージですか?
中村:そうだね。それと、宝船という意味もあるんだ。もし今後、自分で映画を作るとしたら、トレードマークは宝船にしたいね(笑)。
工藤:シネ・キャビンが始動した平成6年くらいは、もう他にピンク映画をやるスタジオは少なかったですよね。
中村:ニュー目黒スタジオという所が、まだかなりやってたけどね。
工藤:まあ、すでに2、3カ所ですよね。当時はどの位の仕事量だったんですか?
中村:月に3本くらいかな。
工藤:その後、徐々に、シネ・キャビンがピンクの仕上げを一手に担う時代が来るわけですが、シネ・キャビンは単なる録音スタジオではなく、ピンク映画に係るスタッフ、キャストの拠点のような役割りを果たしていたと思うんです。
中村:まあ、溜まり場ね。みんな酒を飲んで、泊まってね。民宿とも言われてたよ。
工藤:監督とか助監督とか、その他のスタッフ、キャストもそうですけど、中村さんが、みんなの相談相手になって色々な面倒を見ていたというのがあると思うんです。
中村:まあ、俺も酒が好きだからね。酒を飲みながら話しをして、その程度で済むじゃないですか、男は。その中には愚痴もあるだろうし、他人に言えない事もあるだろうし、「何でも俺に語れば」と。それだけですよ(笑)。若松孝二監督が言ったんだけど、ほら、中国で豪傑が集まる…。
工藤:梁山泊ですか?
中村:そう、梁山泊!若松監督が、「中村ちゃん、ここは梁山泊だね」と言ってたよ(笑)。
工藤:本来は、撮影所があったら、そういう機能なんでしょうけど、ここは撮影所の役割りも果たしていたわけですね。色々な組の人間が集まって交流するという。
中村:俺の狙いもそこだったんだよ。俺は撮影所も知ってるけど、ピンクのスタッフはずっとフリーで撮影所を知らないでしょ。打ち合せ場所とか、交流の場とかそういう「形」を作ってあげたかったの。
工藤:ここが、拠点となって色々なスタッフが出入りすることで、様々な交流が生まれてましたよね。日活時代の先輩の後藤大輔監督が、たまたまここに置いてあった、僕の映画の台本を読んでくれて、後で色々意見を言ってくれたり。それぞれの組に別れちゃうと、なかなか接点が無いですものね。
中村:撮影をやりたいという男がいてね。「それなら、ここにいれば、誰かに知り合えるから」と言って。暫く映写をやってたんだけどね、その後、カメラマンの志賀ちゃんの助手をやって、自分もカメラマンになったんだ。
工藤:映写部から撮影部ですか?
中村:そう、映写機はスイッチを入れれば回るから、何でもいいから、取りあえずやってろと(笑)。
工藤:人生が変わるような、色々な出会いがあったわけですね。交流の場と言う意味では、シネ・キャビンがピンク業界の忘年会と夏の納涼会を主催してたじゃないですか。これの業界に対する貢献はとても大きかったですよね。
中村:忘年会の最初は、銀座サウンドの時代なんだよ。俳優の港雄一さんと仕事した時、銀座で仕事が終わって2人で飲みに行ったんだよ。港さんは「銀座で飲むの?大丈夫?」なんて、心配してるんだけど、俺は、行きつけの店だったんで「大丈夫、大丈夫、何とかなるんじゃない」と、とぼけてたんだ。その時、店の奥でサラリーマンが5、6人飲んでたんだけど、店長が来て「あちらの方々が一緒に飲みたいとおっしゃってるんですが、良いでしょうか?」と。聞いたら、全員港さんのファンだったんだよ。一緒に飲んだら、大盛り上がりになっちゃって、港さんも大歓びだったよ。
工藤:ピンクの俳優さんも、自分が思ってる以上にスターだったわけですね。
中村:そうだね。そんな事があったので、仕事以外で飲める場があるとあんなに喜んでもらえるのかというのと、それと、俺たち録音は夏も冬も快適な部屋の中にいるけど、俳優さんは裸で一年中頑張っている訳だから、ねぎらわなきゃいかんなと思ってたんだ、勝手に。だから、その年、忘年会という形でやったんだよ、銀座で。その時は8人か9人だったと思うよ。それから、毎年、鍋を囲んだりして。シネ・キャビンになってからは、隣に広いスペースがあるから、バーツと机を並べて、ゴザを敷いて。すごい人数が来てたからね、足の踏み場も無いくらい。
工藤:何人くらい来てたんですか?
中村:広い部屋の端から端に3列にテーブルを並べて、入れない人は、スタジオの表で飲んでたから、100人以上いたんじゃないかな。その後、田中スタジオに会場を移してからも、80人は来てたからね。
工藤:実際、交流の場でしたよね。シネ・キャビンの忘年会で知り合った女優さんに、出演してもらった事もありますよ。「おひとりさま 30路OLの性」の友田真希さんなんかがそうです。
中村:普段、全然顔を合わさない連中があそこで出会ったじゃないですか、「中村さん、あの人誰だっけ?」と言うから「同じ仕事してる仲間だよ」と。それで、監督どうしが知りあいになって。監督と助監督もそうだよ。色々な人の意見を聞いたり、先輩の話しを聞いたりというのも大切だよね。まあ、100人や80人と一緒に飲むと言うのは気持ち良いじゃない(笑)。
工藤:昔は昼頃から飲み始めて、翌日の朝まで飲んでましたよね。
中村:それどころか。俺は何年も正月マトモに家に帰った事が無かったもの、29日に忘年会があるとすると何人かは大晦日まで残って飲んでるんだ。そいつらを送り出して、除夜の鐘を聞きながら後片付けをして、元旦に帰った事が何回もあるよ(笑)。

その4「ピンク映画のこれから」に続く