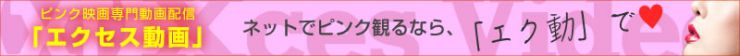ピンクの炎 第2回 「音屋の矜持」シネ・キャビン中村さんに聞く その2「修業時代」
工藤:東映に入社していかがでしたか?
中村:働く事は好きだから、朝1時間前くらいに会社に行って掃除したりして。
工藤:張り切っていたんですね。入社した時は、お幾つですか?
中村:18歳かな。
工藤:若いですよね。配属された部所は?
中村:録音部なの。入れそうなのは、編集と照明と録音があったんだよね。照明はライトとか重い物を持つから嫌だと思った。当時のライトとかって今よりずっと大きくて重いじゃないですか。編集も面倒そうだし、それにもともと音がやりたかったからね。
工藤:録音部といっても色々担当があるじゃないですか。録音部の中で、どんな仕事を担当したんですか?
中村:何でもやるんだよ。映写から、マイクマン、そして効果の生音。やっぱり、一番性に合ったのが生音だったんだよ。好きだったね。録音中は他人が入れない仕事なんだよ。本番中は自分1人。役者と同じなんだ。「これは、人の意見は聞かなくていいよね」と、何か録音技士に言われても「はい、はい」と言いながら、自分の好きな事をやってたよ(笑)。昔は、チャンバラで刀がぶつかる音でも、テープで一音づつ貼り着けるんじゃなくて、生で音を着けていたんだ、全部、ぴったりとね。
工藤:そうなんですか。
中村:最初にやった作品かどうか分からないけど、1本プリントを持ってますよ。昔は、プリントを破棄しちゃんうんだよね。取りに来るんですよ業者が。フィルムから銀を取るんだよね。
工藤:破棄は、もったいないですね。
中村:そうなんだよ。何年かして倉庫がいっぱいになると、保管しきれないんで破棄しちゃう。だから、自分のやったのを、お願いして貰ったんだ。それを、いまでも大事に持ってる。
工藤:当時は、テレビもフィルムで撮っていたんですね。
中村:そう、16ミリ。
工藤:テレビの生音が仕事の中心ですか?
中村:マイクマンとか全部だね。流れとしては、午前中映写をやったら、午後からマイクをやって、夜は別の仕事とか、ローテーションしてたんだよ。
工藤:テレビプロの録音部のというのは何人くらいいらっしゃったんですか?
中村:当時、録音部の助手だけで12、3人いたかなあ。録音技士だけでも4、5人いたから。
工藤:当時はどんなドラマをやってらしたんですか?
中村:分かりやすのだと「特別機動捜査隊」(現在のテレビ朝日であるNETテレビで、1961年から1977年まで放送された刑事ドラマ)。波島進さんなんかが出演してたね。波島さんは、本編でも何本も主演してるよ。俺も子供のころ見たもの。鹿児島出身の人なんだ。それで、現場でも話が合ってね。
工藤:そうですか。
中村:ドラマを週に3本か4本作ってたんじゃないかな。だからフル回転ですよ。家に帰れないから、みんなリンゴ1個もらって旅館に泊まらされて。若いから出来たんだよね。

工藤:その後は?
中村:僕は昭和39年に一度東映を離れたんですよ。その頃、外苑前に新しいスタジオが出来て、人がいなくて大変だから、ちょっと手伝ってやってくれないかと頼まれたんだ。それで、ちょっと様子を見に行っただけのつもりだったんだけど、行ったら、徹夜続きでみんなボケちゃって、何回やっても音が合わない。それで、テープのスタートの位置とか直してあげたら一発で合って。そしたら、明日から是非来て下さいと(笑)。
工藤:でも、東映の仕事もあるわけですよね。
中村:そう。でも、その時、東映だけじゃなく、外の仕事も見てみたいという思いもあった。そこは録音だけのスタジオで、映画会社の中の録音部とは、やり方も違うわけだからね。自分の中では3年くらいは、外の世界も見て勉強したいという気持だった。
工藤:それが後々、シネキャビンの運営に役立つわけですね。
中村:そうそう。
工藤:それは、何という会社だったんですか?
中村:セントラル録音。アニメの「オバQ」とか「鉄人28号」、それと歌舞伎座テレビ(歌舞伎座のテレビ番組制作部門)の仕事が多かったよ。「若様侍」とか「遠山の金さん」とか。その中で、12代目市川團十郎(当時は市川新之介)のデビュー作をやったのを覚えている。15分から30分の帯ドラマをずっとやってた。
工藤:帯ドラマ以外の仕事もあったんですか?
中村:そうだね、映画の仕事もあったよ。黒木和雄監督、原田芳雄さん主演の「龍馬暗殺」の生音をやったのは楽しかったなあ。
工藤:その頃の印象に残る思い出は?
中村:昔、三船敏郎さんが、自分のプロダクションでCMを作ったんですよ。「飲んでますか?」っていうの。
工藤:あっ、覚えてます。
中村:セントラル録音の社長は東宝出身の人だったんだよ。その関係なのかと思うけど、三船さんがその仕事で来たの、うちのスタジオに。
工藤:ほう。
中村:スタジオにレコードのターンテーブルがあるんだけど、俺がCMのナレーションを録っていると、誰か来てゴソゴソし始めた。録音ブースから俺が、「うるさい、静かにしてくれ!」と怒鳴りつけると、「あ、すみません」と振り返る。録音ブースのガラスに映ったのが、三船さんだったんだ。三船さんが、自分で選曲してたんだね。
工藤:三船さんに怒鳴ったりして大丈夫だったんですか?
中村:どうしようかと思ったけど、「まあ、いいや。ナレーション録ってるんだから、今は俺の時間だ、俺が一番でも良いだろうと」と、謝りもせずね。でも、すぐ社長が慌てて飛んで来たよ。「中村君、三船さんに何て事言うんだ!」とね(笑)。
工藤:若造が、世界の三船を怒鳴りつけちゃマズイですよね(笑)。
中村:もちろん、こっちの仕事が終わった後でね、すみませんと頭を下げたよ。なにしろ向こうは三船プロの社長で、会社と会社の関係だからね。でも三船さんは、「いやいや、全然かまわないよ」と。すごく気さくな人なんだよね。
工藤:その後、東映に戻ったんですよね?
中村:何年かして呼び戻されたんだ。当時、ストライキとか組合運動が盛んになって、5時になると社員スタッフがいなくなっちゃう。技士とフリー契約のスタッフしか残らない。だから、俺みたいなフリーのスタッフが必要になったんだよね。昭和42年の12月かな、東映に誘われてたんだけど、盲腸になって入院してたんだよ。手術の後も中々熱が下がらなかったんだけど、24日だったと思う、自分で体温計を振って目盛りを下げて、それで退院して。まだ盲腸は痛いし、腹巻きも取れてなくて、手すりに掴まってやっと歩く状態だったんだけど、年明け早々から東映に行ったよ。
工藤:東映のテレビ部に戻ったんですね。
中村:そう。テレビは連続ドラマだから、続けなきゃ行けないじゃない。ストをやってる仲間は、裏切り者とか思ってたかも知れないけど、テレビの前のお客さんには関係ないし。なんと言われたってやるしかないと思ったね。
工藤:その頃はどんな番組をやってたんですか?
中村:「キカイダー」とかね、子供番組、変身モノの生音をたくさんやったね。生音はやる人が少なかったんだよ。
工藤:その頃はもうビデオですよね?
中村:いや、まだフィルムだよ、16ミリ。昭和40年代は、フィルムだよ。オールアフレコからシンクロになったのは、俺の記憶では「非常のライセンス」(1973年から1980年までNETテレビで放送された刑事ドラマ)から。天地茂さんの当たり役だったね。
工藤:アフレコの上手な俳優さんっていらっしゃいました?
中村:東映時代に凄いと思ったのは小川眞由美さんと野川由美子さん。これに天地茂さん入ってオールアフレコでやるんだけど、まあ聞き惚れちゃったね。例えば、小川眞由美さんは声に幅があって説得力があるの、台詞に。
工藤:説得力ですか。
中村:天地さんも声が良かったね。それに、野川由美子さんは当時、高校生だったんだよ。それが小川さんや天地さんに負けずにやってるんだから驚いた。「孤独の賭け」というドラマだったと思うけど。俺は、奇麗なだけの声は何とも思わないんだよ。大切なのは味というか…。ピンク映画のカラミなんかは特に味が重要だよね。

いよいよ、ピンク映画への進出を語る、その3「処女航海、シネキャビン始動」に続く