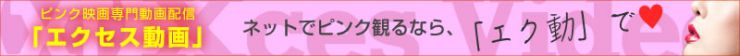ピンクの炎 第2回 「音屋の矜持」シネ・キャビン中村さんに聞く その4「ピンク映画のこれから」
工藤:中村さんが「音屋」として目指した先輩はいるんですか?
中村:いや、特にいないね。誰か1人に師事したという事も無いし、1人で自分の音を求めて試行錯誤してやってきたから。先輩で上手い人はたくさんいたよ。それぞれ個性もあってね。総じて失敗しないやり方を知っていた。俺は、失敗だらけでやってきたけど。
工藤:「失敗しない」ですか?
中村:昔は、光学録音でフィルムが貴重だからね。効果の音付けもフィルムでやってたんだ。フィルムを無駄にできないから、失敗しないで録音することが大切だった。俺の頃はテープだから、まだ色々失敗もできて幸せな時代だったね。映画は、「ウソ」をどう上手く作るかということでしょ。例えば、2時間の作品で1年とか20年とかの話しをする事もあるわけでしょ。映ってるモノは「影」なんだから。なんだかんだ言ったって、俺は「ウソ」を上手く作るのが一番だと思うね。
工藤:中村さんは、リアリズムより「表現」としての音を追及してきたと言う事ですね。
中村:そうです。俺は、工藤監督の作品のエンディングで訊いた事があるんだけど、覚えてる?ラストで女がビルの屋上で1人で立っているの。
工藤:さっき話に出ましたが、2008年の「おひとりさま 30路OLの性」ですね。
中村:そう、主演の友田真希さんが凄く良い立ち姿だったんだ。監督は、ラストに音楽を入れたいと言ってそうしたけど、俺は、効果音で終らせたかったんだよ。今でも、時々思うんだ、あれを効果音で終らせたらどうだったのかと。
工藤:僕も忘れてましたが、そんなに拘って覚えていてくれたんですね。
中村:そう。ビルの屋上に立って女は何かを感じるんだよね。俺は、女の心の音、例えば地震の音とかを入れたかったんだ。
工藤:そうか、僕は随分甘い演出をしちゃったという訳ですね。
中村:いや、監督が音楽でいきたいと言うのは当然だと思うけどね。効果音で終るとか変わったのがあっても良いかなと。「音」で何かを表現するという事は、常に考えているし、これからも挑戦していきたいね。
工藤:素晴らしいですね!
中村:工藤監督の作品で一番好きな映画が、靴屋の…。
工藤:2000年の「ハイヒールの女 赤い欲情」ですね。
中村:あの靴屋のロケセットは自分で探したの?
工藤:自分で電話帳に載っているハンドメイドの靴屋を、片っ端から尋ねていったんですけど、その中に宮内庁御用達の靴屋さんがあって。あの映画は、靴に対するフェティシズムの話しなんですが、そのコンセプトに凄く共感してくれて。でも、自分の店は宮内庁御用達なのでピンクはさすがにまずいと(笑)。それで、友人の靴屋さんを紹介してくれたんです。そこも、パリコレに靴を出品するような店で、良い雰囲気のロケセットでしたよね。オーナーが凄く進歩的な人で、ピンク映画に理解を示してくれて、一番重要な小道具の赤いハイヒールも作ってくれたんですよ。ピンク映画をやってると、時々、お金じゃなくて応援してくれる人と出会えるじゃないですか。そんな時は、涙が出る程嬉しいですよね。
中村:俺は、あのカメラがメチャクチャ好きで。
工藤:撮影の井上明夫さんのカメラですね。
中村:カメラの動きが映画の動きなんだよね。洋画で「ローラ殺人事件」(1947年、監督 オットー・プレミンジャー)というのがあるけど、画がフィックスでズームも無い、移動するときも、こうゆっくりと。それと似てて、「へえ、日本でもこういう風にできるんだと」感心したよ。それから、俺も変わったんですよ、本当に。
工藤:当時、すごく褒めてもらったんで、自信にもなったし、ありがたかったです。あの映画は、俳優のなかみつせいじさんとの始めての仕事だったんですけど、なかみつさんも、良い芝居をしてくれましたね。
中村:全て、何かがマッチしたんだろうね、あの映画は。映画っていうのは奥深いものなんだから、カラミだけ派手にやってれば良い訳じゃないんだ。その辺をプロデューサー連中が分かっているかだよね。
工藤:分かっていて欲しいですね。
中村:映画として良いモノを作らなきゃ長続きしないよ。井上さんのカメラの構図に、久々に映画を見たっていう気がしたんだよね。今の監督は、むしろテレビを意識してるんじゃない?
工藤:ピンクの監督がテレビをですか?
中村:そう2次使用とかの為に。
工藤:ああ、劇場だけでは制作費がペイしないので、BSやCSの放送用にR18
版とR15版の2種類を作ったりしてますね。
中村:とにかく、良いものを創るという事ですよ。2次使用なんて向こうから買いに来させるくらいの気構えでいかないとね。
工藤:先ほど、なかみつせいじさんの話しが出ましたが、中村さんがこれまで仕事をした中で印象深い俳優さんはどなたですか?
中村:俺は、とにかく最後までやる俳優が最高だと思うからね。やっぱり、なかみつせいじに尽きるね。自分の事だけじゃなく、仲間や後輩の俳優の事も考えているし、ピンク映画界への貢献は大きいよ。最近は、出過ぎだというんでベテラン俳優を使わない傾向があって、ベテランの出演が減っているのが悔しいし、残念だね。長年ピンクで頑張ってる俳優、女優こそが、ピンク映画界の宝だって事を、ピンク映画各社のプロデューサーたちには分かって欲しいね。
工藤:ところで、中村さんは、ピンク映画のデジタル化についてはどう思ってらっしゃるんですか?
中村:まあ、デジタルは便利だからね。それはそれで良いと思ってるよ。でも、そもそもフィルムとデジタルは全然違うものだと思ってるから、フィルムが完全に無くなってしまうとすれば残念だね。
工藤:中村さんは、十数年前から、フィルムの世界でも音の分野では徐々にデジタル化していく中で、つい最近まで、頑固に録音は6ミリテープを使って、切った貼ったをしてたじゃないですか。あれは、予算の関係ですか?
中村:もちろん予算もあるけど、6ミリテープの音が好きだったからね。とにかく、フィルムでピンクをやる人がいる限りは、誰が最後の1人になろうとやってやろうと思ってた。フィルムのピンクは平成27年、一昨年の9月で終ったけど。

工藤:これから、シネキャビンをどうしていこうとお考えですか?
中村:大体、先は見えた気がするんだよね。最近、ちょっとそんな風に思う。まあ、どうするか?酒でも飲んで、ゆっくり考えようか(笑)。
工藤:中村さんの考えるピンク映画の未来は、悲観的な未来ですか?
中村:そんな事はないよ。ただ、これをみんながいつまで続けるか。それと、今のやり方ね。それは、フィルムとかデジタルとかじゃなくて、本質的な映画の作り方。「今、これが流行っているからこっちに行こうよ」とそういう動き方をするのか、「いや、これで良いんだ」と自分のやり方を貫くのか。どちらが、良いと思う?
工藤:それは、自分の考えを貫きたいですよね。
中村:そうだね。その方が個性も出るし。俺は、きっと出来ると思うよ。誰かやってくれるんじゃないかと思って、俺は待ってる。映画に、新しいも古いも無いから。変わるのは時代だけ。人間は、そんなに変わりやしないよ。
工藤:自分を時代に合わせるんじゃなくて…。
中村:時代が俺に合わせろ(笑)。
工藤:最後にエクセスフィルムに、何かエールを送っていただけますか?
中村:とにかく最後まで製作を続けて欲しいよね。何かを考えさせる、感じさせる映画を作って欲しい。そして俳優さん。誰でも良いという訳にはいかないよね。それをきちんと演じられる俳優さん。そういう所から多分始まっていくんでしょうね。話の内容はね、あまり暗くしちゃあダメだし、ほのかに明るく終るようなエンドが良いのかな。
工藤:なるほど。
中村:お客さんが「これからだ!」という気持ちになれる事。それも、女じゃなく男が。
工藤:男に夢を持たせるピンク映画ですね(笑)。
中村:俺たちが若い頃、映画で石原裕次郎を見て、皆その気になって、マネしたじゃないですか。幾つになっても同じだと思うよ。それは、形じゃなくて心だと思う。
工藤:本当にそうですね。
中村:それと、バラエティが欲しいよね。シリアスがあって喜劇があって。上手く撮れれば、俺は喜劇が見たいね。普通の生活は、今してる訳だから、実際はあり得ない生活、本当にバカバカしいけど、「こんな生活がしたいよな」というような。
工藤:「未亡人下宿シリーズ」とか、そういう喜劇がピンク映画にはありましたね。
中村:あれをもう一回やっても絶対受けるよ。あのタッチで。しゃべりの間も良いし、台詞も良いし。でも、今、それを出来る役者がいないんだよね。みんんな真面目だから、自分を捨てて違う世界に行ける俳優さんは少ないよね。
工藤:若い頃の久保新二さんなんか、自分を捨てているというより、映画のままの人だとしか思えないですよね。久保さんは自分を捨ててるんですか?
中村:捨ててるんだ。全部芝居だよ。だから凄いんだ。自分じゃないから、ああいう芝居が出来るんだよ。
工藤:久保さんをはじめ、当時の俳優さんはアフレコの技術にも長けていたんですか?
中村:そうだね、みんな自分の間で芝居をするからね、だから魅力がある。相手の間に合わせないから、火花が散るガチンコの勝負になる。
工藤:そういう芝居のぶつかり合いが面白かったんですね。女優さんも芝居でぶつかって来ると。
中村:そうだね、今じゃ考えられないけどね。みんな上手かったんだよ。そういう俳優さん、女優さんにまた出て来て欲しいね。
工藤:中村さん、ご自身でプロデュースしようというお考えはありますか?
中村:出来れば……ね。
工藤:まだまだ、映画人生は続きますね。今日はどうもありがとうございました。
終